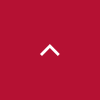【基礎知識】インセンティブとは?制度を導入するための設計方法と導入事例
「インセンティブ制度を導入したい」と考えつつも、インセンティブについていまひとつ理解が足りないと悩む人事・営業部門担当者、もしくは経営層も少なくないでしょう。インセンティブ制度は従業員の労働意欲を刺激する効果的な方法ですが、意義を深く理解していなければ、制度設計が立ち行きません。インセンティブ制度を成功させるための基礎知識と設計手順を紹介します。
【関連資料】
従業員に喜ばれるギフトカードの選び方については、以下のお役立ち資料も
ご参照ください。商品券や現金との比較についても紹介しています。
「感謝の気持ち」を伝えるためのギフトとは?従業員が貰ってうれしいギフトの選び方や注意点
目次[非表示]
- 1.インセンティブとは
- 1.1.インセンティブの意味
- 1.2.インセンティブ制度
- 2.インセンティブと歩合の違い
- 3.インセンティブ制度を導入するメリット
- 3.1.①従業員のモチベーションが向上する
- 3.2.②組織の成長にもつながる
- 3.3.③多様な支給が可能で、かつ運用の手間が少ない
- 3.4.④社外パートナーとの関係性を良くするのに利用できる
- 4.インセンティブ制度の導入にあたり直面する課題
- 5.インセンティブ制度を設計する方法
- 5.1.①目的の明確化
- 5.2.②対象ニーズの把握
- 5.3.③インセンティブ制度の内容を決める
- 5.4.④社内周知
- 5.5.⑤実施と改善
- 6.インセンティブ制度の導入事例
- 7.インセンティブの意味や効果を知って、モチベーション向上に役立てよう
インセンティブとは
まずはインセンティブの意味と効果を見ていきます。
インセンティブの意味
インセンティブは日本語で「報奨」「奨励」「刺激」などと訳されます。目標を達成して成果を上げた従業員に対して支給される報奨金などを指すのが一般的です。
インセンティブの種類は豊富で、必ずしも支給されるのが「現金」とは限りません。「物質的インセンティブ」と呼ばれる、お金やモノを支給するインセンティブや、成果に対して評価を与える「評価的インセンティブ」、従業員の希望を実現する「自己実現的インセンティブ」などがあります。
本記事では、もっとも一般的な「物質的インセンティブ」を前提としてメリットや課題を見ていきます。
他のインセンティブについて詳しくは下記もご覧ください。
「インセンティブの種類はどれくらい? 種類ごとの特徴と制度を導入するポイント」
インセンティブ制度
ビジネスにおいては多くの場合、インセンティブによる外的な働きかけにより、従業員の意欲を引き出すことが可能です。つまりインセンティブ制度は、社内的にはモチベーション向上に有効な制度といえます。
インセンティブと歩合の違い
インセンティブと似た用語に「歩合」があります。企業や利用場面によってはインセンティブと同様の制度として用いられることもありますが、両者は厳密には異なります。一般的な違いは次のとおりです。
<インセンティブ>
●目標達成に対する評価で、現金を支給したり、給与を支払ったりすること
●支給形式は必ずしも現金であるわけではなく、モノや金券などを支給することも多い
<歩合>
●売上、契約などの「成果」に対し、所定の割合で一律で支給される
●基本給に加えて現金支給される、給与形態の一種
ボーナスとの違いについては下記をご覧ください。
「インセンティブとボーナスはどこが違う? インセンティブのメリット・デメリットも詳しく紹介」
インセンティブ制度を導入するメリット
社内でインセンティブ制度を導入すると、どのようなメリットが得られるのでしょう。
①従業員のモチベーションが向上する
実績が評価されインセンティブを受け取れることで、従業員のやる気が向上します。頑張りが認められることは仕事への満足度向上にもつながると予測されます。また、派遣やパートなどの、異なる給与体系の従業員も対象としやすいです。
②組織の成長にもつながる
従業員のモチベーションを刺激し、健全な競争意識を芽生えさせることができます。また、評価的インセンティブや自己実現的インセンティブの場合は、従業員の組織に対する信頼感を増し、エンゲージメントの向上に役立てることも可能です。組織の成長や活性化が期待できます。
③多様な支給が可能で、かつ運用の手間が少ない
物質的インセンティブでは、現金以外にも従業員に喜ばれる「モノ」や「金券」を支給する選択肢もあるため、対象者の希望に沿った制度設計が可能です。
また、支給形式が多様であるため、現場の状況やインセンティブの目的に応じて柔軟に運用できます。例えば、「チームワークは良いが個々の企画力が不足している」場合に、良い企画を出した者に対してインセンティブを支給するなど、自社の弱みを補完するかたちでの制度設計も可能です。
④社外パートナーとの関係性を良くするのに利用できる
社内向けのインセンティブ制度のみならず、社外に向けたインセンティブ制度もあります。例えば、「代理店の担当者」「業務委託している個人事務所やフリーランス」に対してインセンティブを贈る方法があります。このケースは、報奨ではなく感謝の意を伝えるインセンティブ制度といえるでしょう。
なお、社外向けのインセンティブ制度は、企業活動の一環として利用できるのがメリットです。例えば、条件を満たした顧客や資料請求者にインセンティブを贈るといった、営業・販促キャンペーンなどでも広く活用されています。
インセンティブ制度の導入にあたり直面する課題
インセンティブ制度は、目的に応じて柔軟に活用できる一方で、運用管理の負担が重くなるといった課題に直面する場合があります。具体的には、現金や金券を支給する際の「保管」「盗難対策」「棚卸業務」「会計上の資産計上」などのさまざまな業務の発生です。モノを支給する場合でも、「購入」「保管」「盗難対策」などの業務が発生します。
また社内では、インセンティブの獲得そのものが仕事をする目的になってしまい、過剰な競争意識が芽生えるといった懸念もあるでしょう。インセンティブが発生する仕事にだけ意欲が偏るといった弊害が生じてしまう場合は、ルールの明確化や公平感を大切に、適切な制度設計を立てましょう。インセンティブ制度の設計については次章で紹介します。
上述のように、インセンティブを現金や金券で支給する場合は管理業務に手間が発生しますが、支給形式を変更することで負担を軽減することが可能です。管理の課題を克服した成功例を紹介します。
NECパーソナルコンピュータ株式会社の事例
NECパーソナルコンピュータ株式会社では、販売スタッフの成績に応じたインセンティブを金券で支給していました。しかし、スタッフごとに支給金額が異なるため、準備にかかる煩雑な業務に苦慮していました。そこで金券の代わりに、プリペイドカードの「バニラVisaギフトカード」を導入したのです。導入効果は高く、これまでの課題を解決できました。バニラVisaギフトカードを導入した一番の決め手は、3,000円以上10万円以下の範囲で任意に金額が指定できることでした。
「バニラVisaギフトカード」を導入した効果
●販売成績に応じたそれぞれの金額のインセンティブを、スタッフ1人に1枚のカードで渡せるようになり、封入や保管など準備にかかる時間が激減した
●利用者が有効化するまで金券として管理する必要がないため、贈呈前の金券管理や、贈呈後の運用・報告などにかかる手間も削減された
インセンティブ制度を設計する方法
インセンティブ制度を設計する手順を紹介します。
①目的の明確化
「目標達成のために営業部のモチベーションを上げたい」「全社的に、頑張っている従業員を評価したい」など制度の目的を明確化します。
②対象ニーズの把握
インセンティブ制度対象者の労働意欲を刺激するためには、相手が喜ぶインセンティブを用意することが重要です。インセンティブの種類は多いからこそ、対象が何に魅力を感じるのかヒアリングして、種類や価格帯を絞っていきます。
③インセンティブ制度の内容を決める
だれが、何を達成すると、どんなインセンティブが支給されるのかを決定します。例えば、営業部員が対象のインセンティブであれば、「チームごとに半期目標を達成したら、チーム全員に対してインセンティブを支給」「営業成績・チームサポート・指導などを総合的に評価して毎月1名をMVPとして選出し、インセンティブを支給」などが考えられます。
④社内周知
導入目的を共有します。もともと「モチベーション不足」「頑張っている人が適切に評価されにくい」などの課題があり、それを克服するための制度であると説明すると理解を得られやすく、効果が高まるでしょう。
⑤実施と改善
インセンティブ制度の実施後は効果を測定し、改善すべき点を見つけていきます。継続的にPDCAを回していくことで、改良を図ります。
インセンティブ制度の導入事例
インセンティブ制度を導入した事例を3つ紹介します。
事例1:全社的な士気を高めるためのインセンティブ制度
<保険代理店>
契約件数や売上、営業現場での取り組みなどに対してポイントを支給するインセンティブ制度を導入しました。貯まったポイントの使途は本人が自由に決められるのが魅力です。
営業職だけでなく、営業職を支える社員、また社員だけでなくパート職の人材など幅広い層をインセンティブ対象者に設定したのが特徴です。インセンティブ制度が起爆剤となり、部門やチームの目標達成を個人レベルまで落とし込むことに成功しました。個々のモチベーション向上にも大きく寄与しました。
事例2:外国人スタッフから評価の高いインセンティブを支給
<外資系メーカー>
業績好調により、全社員を対象にインセンティブを支給することになりました。しかし外国人スタッフが8割以上を占めるため、インセンティブの選択に迷っていたのです。日本国内のオンラインショップやサービスで利用できるデジタルギフトは不向きで、スマートフォンを利用するタイプのギフトコードも、個々が保有する機種が対応可能か不明で採用できませんでした。
このケースでは、デジタルギフトの「Visa eギフト バニラ」を利用しました。国内外で認知度の高いVisaは外国人スタッフにも大いに喜ばれました。
事例3:登録会員向けにインセンティブを活用
<中古自動車オークション事業の会社>
SNSに登録した会員に向けて、インセンティブを支給することを決定しました。SNSの会員登録に由来するインセンティブなので、デジタルギフトであることは必須条件でした。準備期間が短かったため、「使える先が多い」ことも重視されました。結果として、利用先の豊富な「Visa eギフト バニラ」を採用したところ、サービス利用頻度が向上しアクティブ会員が増加しました。
インセンティブの意味や効果を知って、モチベーション向上に役立てよう
インセンティブ制度は、モチベーション向上に貢献する有益な手段ですが、導入方法を誤ると効果が半減してしまいます。インセンティブ制度を成功させるためには、インセンティブとは何かを理解したうえで制度設計することが重要です。
また、インセンティブが金券・商品券などの場合は、紛失・盗難防止のための厳重な保管業務や、会計処理、棚卸業務などの管理に手間がかかるのも課題でしょう。「バニラVisaギフトカード」や「Visa eギフト バニラ」なら、有効化されていない状態で納品されるので、金券扱いで保管する必要がありません。そのため、管理業務が効率化できます。また、利用する際の審査や個人情報の登録などが必要なく、クレジットカードなどと同様に気軽に買い物で利用できます。
プリペイド式の「バニラVisaギフトカード」は、カードの実物を封入して届けたい場合や、ギフト梱包したい場合におすすめ。 Visa加盟店であれば、オンラインだけでなくオフラインの店頭や、海外でも使用できて便利です。「Visa eギフト バニラ」は、オンライン上でのやりとりで済むデジタルギフトです。 Visa加盟店のオンラインショップで利用できます。実物を伴わないため、支給する際の労力やコストがかからない点や、500円の小額から金額を指定できるといったメリットがあります。
目的や効果の達成と、負担の無い運用を両立させるインセンティブ制度を構築していきましょう。