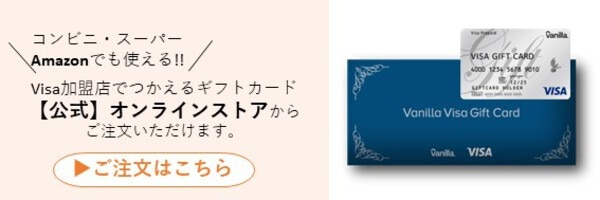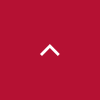出産祝いに喜ばれるもの6選!贈るタイミングやマナー、相場についても解説
出産祝いは、新しい生命の誕生を祝う気持ちを表す、特別なお祝いです。そのため、本当に喜んでもらえる贈り物を選びたいものです。しかし、出産祝いに何を選べばいいか、いつどのように渡せばいいか悩む方も少なくないのではないでしょうか。
今回は出産祝いについて、贈るタイミングやマナー、贈り物の相場、喜ばれやすいものの選び方などをご紹介します。
目次[非表示]
- 1.出産祝いの基本
- 1.1.出産祝いを贈るタイミングは?
- 1.2.出産祝いを渡すときのマナー
- 1.3.出産祝いを渡す方法
- 2.出産祝いの相場
- 2.1.兄弟や姉妹に贈る場合
- 2.2.いとこや近しい親族
- 2.3.親戚
- 2.4.知人やご近所の方
- 2.5.会社や仕事の関係者
- 3.出産祝いでもらって嬉しいもの6選
- 4.出産祝いでNGなもの
- 5.出産祝いは贈る相手にとって負担にならず使いやすいものを
出産祝いの基本
出産祝いは従来から存在する慶事の1つであり、身近な親族や親しい間柄でも渡す贈り物です。そのため、お祝いの気持ちを込めつつ失礼のないように渡したいものです。出産祝いについて、贈るタイミングやマナー、渡す方法などについて見ていきましょう。
出産祝いを贈るタイミングは?
出産祝いは生後7日から1ヶ月の時期に渡すのが一般的です。
生後7日には「お七夜」と呼ばれる名前を披露する儀式が行われる地域があり、生後1ヶ月には赤ちゃんの健康と成長を祈るお宮参りが行われます。出産祝いを渡すのは、このお七夜のあとからお宮参りの前までの期間が目安となります。
ただし、帝王切開やその他の事情によっては、生後7日後でもまだ母子ともに入院中の場合もあります。退院していたとしても、退院直後は落ち着いていないご家庭も少なくないため、贈る相手の都合を確認したうえで贈ることが望ましいでしょう。
これらのことを合わせて考えると、生後2~3週間の時期がベストなタイミングと言えます。
出産祝いを贈るタイミングについては、こちらでも詳しく解説しておりますのでご覧ください。
出産祝いを渡すときのマナー
基本的に出産祝いは「出産後に渡す」もので、産前に渡すのはNGです。
「産後は忙しいだろうから」と気を使ったつもりでも、そもそも出産祝いは赤ちゃんが無事に生まれたことを祝うものだということを忘れてはいけません。出産は何が起こるかわからないため、産後に母子ともに健康であることを確認してから贈りましょう。
また、出産祝いを渡す際は一言お祝いのメッセージを添えて贈るといいでしょう。その際、当然ながら「病」「切」「死」といった忌み言葉は使ってはいけません。
また、赤ちゃんの健康を願う気持ちで「大きく育って」「たくさん食べて」「ミルクをいっぱい飲んで」といった表現も避けたほうが無難です。赤ちゃんの成長は波があります。なかなか体重が増えない場合やミルクを飲んでくれない時期もあり、それについて悩むご両親もいるため、プレッシャーになりかねません。
出産祝いを渡す方法
出産祝いは慶事であり、のしを付けて渡すのが一般的です。出産は何度あっても喜ばしいこととされるので、紅白の蝶結びの形になっている花結びの水引を選びます。
のしの表書きは「御祝」「御出産御祝」「ご出産祝い」「御安産御祝」などを用います。「祝御出産」や「御出産祝」は4文字になり好ましくないとされる場合もあります。
お品物を持参する場合には、風呂敷に包んだり袋に入れたりして持っていき、風呂敷や袋は持ち帰りましょう。
現金の場合はご祝儀袋にお祝い金を入れ、ご祝儀袋を「袱紗(ふくさ)」で包んで持参し、袱紗から取り出して相手が字を読める向きで渡すのが一般的な作法です。袱紗は慶事用と弔事用があるため、必ず慶事用を使いましょう。
基本的に、出産祝いを病院に持っていくのは避けるべきです。以前は出産後に入院中の母子の元へ訪問し、病院で出産祝いを渡すという方法もありましたが、感染防止や母子の体調を考慮して面会を禁止しているケースが少なくありません。
また、ご自宅に持参する場合は、必ず相手の都合を聞いてからにしましょう。「お祝いを持ってきてくれたのだから」と気を使い、無理をさせてしまう可能性もあります。お祝いの気持ちを届けるので、相手の負担にならない方法を選択することが重要です。
メッセージを添えた出産祝いを配送しておき、実際に対面でお祝いの言葉を伝えるのは後日という選択も、失礼には当たりません。お母さんや赤ちゃんのことを考えた選択として喜ばれるでしょう。
出産祝いの相場
出産祝いの金額について迷う方も少なくないのではないでしょうか。いくらくらいの金額で贈るか迷う場合は、一般的な相場にそって決めるといいでしょう。
出産祝いの相場は贈る相手との関係性によって変わります。また、地域の風習や自分側の立場によっても変動するので注意が必要です。
兄弟や姉妹に贈る場合
贈る相手が兄弟や姉妹の場合、1~5万円が一般的な相場です。ただし、こちらが学生の場合は無理のない金額を選びましょう。
いとこや近しい親族
いとこや近しい親族の場合は、1~2万円が相場となります。もし、以前にこちらがもらっていればその金額に合わせます。
親戚
親戚とのお付き合いは、地域の風習や親族間の考え方などによって贈る範囲が変わるため、親族で相談して決めるのがいい場合もあります。一般的には1~3万円の範囲が相場となり、これまでの関係によって選択するといいでしょう。
知人やご近所の方
知人やご近所の方に対しては、3千円程度が一般的です。以前にこちらがいただいていれば、その金額に合わせます。
会社や仕事の関係者
会社や仕事の関係者へ贈る場合、自分と相手の立場によって相場が異なります。送る相手が部下や同僚の場合は3~5千円、上司や先輩に対して送る場合は5千円~1万円が相場です。部署やチームで「一同」として送る場合は、メンバーで相談して決めましょう。
出産祝いでもらって嬉しいもの6選
実際にどのようなものを出産祝いとして贈ると喜ばれるのでしょうか。出産祝いとしてもらうと嬉しいもの、贈って喜ばれるものとしておすすめのものを6種類ご紹介します。
ギフトカード
さまざまなお祝いやプレゼントとして使われているギフトカードは、出産祝いにも適していて喜ばれる贈り物です。
ギフトカードは、贈った相手が必要なものや好きなものを選ぶことができます。そのため、受け取った側で贈り物が重複するということがありません。
例えば、ベビーバスのように育児期間に1つあれば足りるものが複数の人から贈られた場合は、送る側、もらう側どちらにとっても嬉しいことではありません。その点、ギフトカードであればもらう側が必要なものを選べるため、お祝いを育児に有効に使ってもらえます。
また、ギフトカードは現金より直接的でなく、柔らかな印象を持たれます。
遠方からも手軽に送れるため、直接訪問できない距離にお住まいの方にもお祝いを贈ることができます。また、贈る相手の体調や都合に配慮して自宅を訪問せずに届けることも可能です。
手渡しの場合でも、カードの状態であればコンパクトでかさばらないため持参しやすく、もらった側も保管に困ることがありません。特に、初めての出産の場合、何が必要になるかわからないという方も少なくないため、実際に必要なものができるまで保管しておくという使い方もできます。ギフトカードは、さまざまな面から出産祝いに適した贈り物と言えるでしょう。
バニラVisaギフトカードは、Visaクレジットカードと同じように多くの店舗やECサイトで使うことができます。自由に好きなものを買えるので、贈った相手はもちろん、そのご家族にもにも喜ばれるでしょう。
お祝い金
現金はお祝いにもらって嬉しいものとして上位に入ります。
1人目の子どもの場合、「これから何が必要かわからない」という方も多く、使いみちの限定されない現金は有効的に使えます。2人目以降の場合、服や食器類など「物」は、上の子のものが使えることがあり、自由に使える現金がありがたがられるケースは少なくありません。
ただし、現金ではあまりに直接的と考える方もいらっしゃいますので、生々しさを避けたい方はギフトカードなど他の選択をするといいでしょう。
ベビー服
ベビー服は、やはりもらってうれしい贈り物です。赤ちゃんの時期はいくつあっても困りません。しかし、注意点もあります。
赤ちゃんがすぐに着られるサイズは50~60程度ですが、そのサイズはすでに両親や祖父母など身内が買っている場合もあります。そのため、70や80など、しばらくしてから着られる大き目のサイズを選ぶのがおすすめです。
ただし、赤ちゃんは個人差が大きく、赤ちゃんに着せるタイミングがないまま、そのサイズを着られる期間が過ぎてしまうこともあるので注意しましょう。また、赤ちゃんがその服を着ることになる季節を考慮して素材を選ぶことも大切です。
おむつセット
おむつもたくさんあって困らないものです。
おむつケーキのように見た目も可愛く、お祝いの意味を込めてパッケージされたものはお祝いにも適しています。ただし、使うおむつの銘柄を決めている方もいるので、事前に聞いてから贈るのがいいでしょう。
タオル
タオルは子育てに欠かせないアイテムの1つです。もし赤ちゃんの時期に使わなくても、大きくなってからでも日用品として使い続けることができます。
性別やサイズを考える必要がないので選びやすいのもポイントです。お祝いなので上質なものを選ぶといいでしょう。
離乳食セット
洗いやすいスタイやベビー用食器などが一揃えになった離乳食セットも、赤ちゃんの成長過程で欠かせない子育てアイテムです。
離乳食セットは、一般的に生後6ヶ月くらいから必要になります。生後すぐに使うものではないため、他の人の贈り物とかぶりにくいというのも選びやすいポイントです。ただし、2人目以降の場合は上の子で使ったものを使う場合もあるため、確認してから贈るといいでしょう。
出産祝いでNGなもの
お祝いの場における贈り物の原則として、ハサミや刃物などは縁が切れることを連想させるためNGです。
最近は気にしないようになりつつありますが、ハンカチもお祝いとしてはNGとされることがあります。ハンカチは日本語で「手巾(てぎれ)」と書き、「手切れ」を連想させるためお祝いとしてはふさわしくないと考えられることがあるためです。
また、弔事で多用される日本茶も、お祝いごとには不向きな品です。
ベビー用品の中では、ベビーベッドやベビーカー、ベビーサークルなど、大型で置き場所に困ってしまう可能性のあるものは、確認せずに贈るのは避けるべきです。1つあれば足りるものであることも多く、レンタルするケースも少なくありません。「大型で置き場所をとるもの」「1つあれば足りるもの」は事前に確認するか、出産祝いの選択からは外すのが無難です。
一般的に喜ばれる贈り物でも、出産祝いとしては適さないものもあります。
お花は一般的なお祝いの品ですが、赤ちゃんのお世話で手一杯な時期に、もらっても困るという方も少なくないので喜ばれないこともあります。
このように、出産祝いは贈る相手の負担にならずお祝いの気持ちが伝わるような贈り物が適しています。
出産祝いは贈る相手にとって負担にならず使いやすいものを
出産祝いについて、贈るときのタイミングやマナー、金額の相場、喜ばれる贈り物などをご紹介しました。
出産祝いは、出産をお祝いしたい気持ちを届ける大切な贈り物です。しかし、出産直後という気を使うタイミングで渡すものですので、贈るものの選び方や送り方も十分に考えて、相手に負担にならないようにしなければなりません。
お祝いする相手に本当に喜んでもらうためには、負担にならず必要なものを選んでもらえる贈りものを選ぶといいでしょう。
バニラVisaギフトカードは、相手が好きなもの、必要なものを自由なタイミングで選んでもらえ、のしやメッセージ添付のサービスもあるため、出産祝いとしても最適です。
バニラVisaギフトカードについて詳しくは、以下からご覧ください。