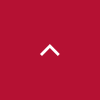記念品をオリジナルで作成するメリットは? 作成の流れや費用感も
周年記念行事や社内イベントなどで、オリジナルの記念品を社内・社外向けに贈ることは少なくないでしょう。記念品を贈ることで、従業員の意欲向上や取引先との関係性の向上など、さまざまな効果が期待できます。しかしその一方で、記念品の作成には一定の手間とコストがかかります。自社で作成するならば、メリットやかかる手間を事前に確認したうえで、作成する意義があるか見極めるべきでしょう。
そこで、オリジナルの記念品を作成するメリットと注意点、作成の流れを紹介します。
周年記念行事や社内イベントなどで従業員がもらって嬉しいギフトの種類や導入事例、メリット・デメリット、注意点は以下のお役立ち資料でも詳しく解説しています。ぜひ合わせてご覧ください。
【お役立ち資料】
「感謝の気持ち」を伝えるためのギフトとは?従業員が貰ってうれしいギフトの選び方や注意点
目次[非表示]
オリジナルの記念品を活用する場面は?
企業がオリジナルのグッズや記念品を自社で作成する場面を紹介します。対象は大きく「社内向け」「社外向け」に分けられます。
●周年記念・創立記念の贈り物として作成
従業員や取引先、もしくは顧客などに対して贈ります。
●事業拡大に伴う移転や開店祝いとして作成
従業員や取引先、もしくは顧客などに対して贈ります。開店祝いの場合は来店客に贈ることもあるでしょう。
●成約記念として作成
成約に至った感謝と今後の取引継続の気持ちを込めて、取引先へ贈ります。
●社内イベントや商品のプロモーションとして作成
社内イベントを盛り上げるアイテムや販促物として作成し、主に顧客や見込み客に対して贈ります。
社内向けの贈り物には、組織全体や個人向けなどがある
社内向けの記念品は、贈る対象が企業・部署のような組織の場合と、個々の従業員の場合に分けられます。また、個々の従業員に贈る記念品は、「全従業員向け」と「特定の従業員向け」の2種類があります。前者は比較的安価なグッズを従業員全員に配布します。一方後者は、永年勤続表彰や退職記念品などが該当し、対象人数が絞られ、高価な品物となる傾向にあります。
オリジナルの記念品を作成するメリットと注意点
主に自社の周年記念行事を例に、オリジナルの記念品を作成するメリットと注意点を紹介します。
オリジナルの記念品を作成するメリット
●全従業員への記念品を作成する場合
オリジナルの記念品によって、行事の印象を残すことができます。行事による意欲向上が一過性のものになるのを防止することができるため、行事終了後のモチベーションアップの継続にもつながります。
また、全従業員がオリジナルの記念品を共有することで、仲間意識が芽生えることも考えられます。結果として、チームワークの向上や、帰属意識の高まりを得られる可能性があります。
●社外向けの贈り物として記念品を作成する場合
創立記念を迎える企業が、取引先に記念品を贈るケースです。オリジナルの記念品を作成することで、自社をアピールをすることができます。創立記念イベントで自社の安定性を感じてもらいつつ、記念品も添えることで、良好な関係性の構築、もしくは良好な関係性の継続が見込めるでしょう。
オリジナルの記念品を作成する際の注意点
社内向け・社外向けにかかわらず、オリジナルの記念品を作成する場合に注意したいのは次のような点です。
●準備期間に余裕をもたせる
記念品の作成は手際よく進めなければいけません。段取りが悪いと、期日に間に合わなくなる懸念があります。作成の流れについては後述します。
●手間や経費が発生する
オリジナルの記念品作成には、企業名やメッセージを名入れするといった手間や経費が発生します。手間がかかれば担当者の負担になり、経費が大きい場合は企画として評価されないかもしれません。オリジナル記念品を贈るメリットを享受するためには、手間や経費を考慮しながら、受け取った相手が喜ぶ品物を選択することが大切です。
記念品の選び方やマナーについては、以下の記事をご参照ください。
周年記念品にはどんなものを選べばいい? 商品例や他社事例、マナーを紹介
また、社内向けの場合は特に次のような注意点があります。
●全従業員を配布対象としない場合は福利厚生費に該当しない
記念品を福利厚生費として処理する際は、原則として「すべての社員に記念品を与える機会が平等にあること」が前提です。オリジナルの記念品を作成する場合は、既製品の商品を購入する場合に比べ費用が上乗せされますが、予算が足りないからと安易に対象範囲を絞って、「管理職のみに贈る」「正社員のみに贈る」といったことがないようにしましょう。
また、オリジナルの記念品によって帰属意識の高まりを期待する場合、周年記念行事そのものが成功しないと意欲向上につながらないという問題点があります。周年記念行事を成功さるためのポイントは、以下の記事で紹介しています。
周年記念とは? 開催する意義や流れ、成功のポイントを解説
オリジナルの記念品を作成する流れや費用
オリジナルの記念品を作成する場合の大まかな流れと費用を紹介します。
作成する流れ
1:見積り依頼と見積書送付
商品・商品数・個別方法の有無などの情報とともに、作成企業に見積もりを依頼します。サンプルが欲しい、デザイン面で相談があるなどの場合はそれらもあわせて相談します。Webサイトの問合せフォームやEメール、または電話で依頼します。
一般的に、在庫確認や見積依頼書の内容に応じた見積書が後日送付されます。既製品への名入れをする場合は、サイトで商品(既製品)を選び、その場で名入れ費用込みの見積もりや配達日がわかるサービスもあります。見積書が届いたら、価格、納期、納品方法などを確認します。
準備期間が少ない場合は、既製品の活用がおすすめです。一方で、オリジナリティの高い記念品を作成したい場合は、企画やデザインなどのサポートが手厚いサービスを選ぶとよいでしょう。
2:注文・データ入稿
見積書の内容を確認したうえで注文します。注文時には、名入れのためやオリジナルで入れたいデータも入稿します。データを新規でデザインしたい場合は、あらかじめ準備しておけばスムーズに注文できるでしょう。デザインを委託できる場合もありますが、別途デザイン料がかかります。
注文後に請求書が送付され、代金を支払うことが多いです。
3:サンプル品の作成・調整
オリジナリティの高い記念品の場合は、サンプル品を確認して微調整を行います。既製品への名入れであれば、この工程は省略されることが多いです。
4:納品
商品が納品されます。
上記の期間は、既製品への名入れの場合、名入れデータ入稿から約2~3週間が目安です。オリジナルグッズの場合は、企画やサンプル品を確認しての微調整が入るので、さらに長い期間が必要となります。
作成にかかる費用
既製品への名入れの場合、商品代のほかにかかる費用は主に次の3つです。
●版代
印刷用の「版」を作成する費用です。原則として、版のサイズが大きいほど高くなる傾向です。1回の注文に対して定額で価格が出ます。印刷方法や使用する色などによっても金額は変わるため、一概にはいえませんが、目安は5,000円〜12,000円程度です。
●名入れ代
名入れ代は、1個あたり10円~120円程度です。注文個数に応じて金額も大きくなります。
●サンプル品代
サンプル品が有料のケースもあります。なお、サンプル品作成と発送には数日かかるので、サンプル品を確認する場合は納期に余裕をもって注文しましょう。
既製品への名入れであれば、商品自体はすでに完成しているため、データ作成や調整の手間はそこまでかからないでしょう。一方で、ゼロからオリジナルグッズを作成する場合は、企画サポートやデザイン委託の有無など、事例ごとに作成期間や費用も異なります。そのため、あらかじめ定められた期日や予算で作成できるかどうか、見積もりの段階でよく判断したうえで依頼するようにしましょう。
オリジナルの記念品は手間と費用も考慮して作成しよう
オリジナルの記念品は、従業員へ贈ることで、モチベーションアップや帰属意識の向上が期待できます。また、社外向けに贈る場合も、自社経営や商品に対するよいアピールにつながるでしょう。
しかし、オリジナルの記念品は作成費用がかかるうえ、発注までの手間もかかります。見積もりやサンプル品依頼のやりとり、納期調整などが必要になり、想定以上に費用がかかってしまうことも考えられます。行事を執り行う部署が記念品の準備も同時に進行する場合、担当者の負担が大きくなるかもしれません。企業側で担当者のサポートをする、人材を増やすなどし、進行に支障が出ないように配慮しましょう。もしくは、準備に負担がかからない記念品を選択する方法もあります。
「Visaギフトバニラ」は世界中のVisa加盟店で利用でき、発行価格は1円単位で設定可能なため、予算との調整もしやすいです。
プリペイドカードタイプの「バニラVisaギフトカード」は、実店舗とオンラインショップで利用できます。
デジタルギフトタイプの「Visa eギフト オリジナルカード」は、オンラインショップで利用できます。カードのデザインをオリジナルに作成し手渡しすることも可能です。
オリジナルデザインに興味がある方はこちら